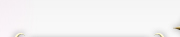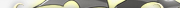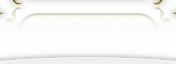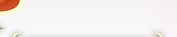「武術の神がおるならば、まさしくその化身じゃな」
W・O・OZ――数々の武勇譚を持つ大英雄、
バロン・ミュンハウゼン――彼をしてそう言わしめるほどの武道家の存在を聞かされた時、
ドロシーは思わず身震いした。
幼い頃ミュンハウゼンによってその才能を見出され、体術の全てを叩き込まれた一番弟子。
若竹のようなしなやかさと鋼の如き強靭さを併せ持つ鍛え上げられた肉体で、
先の魔法大戦においても自らの数倍はあろうかという巨躯の魔物の群れを相手取り、
その研ぎ澄まされた拳技のみで戦い抜いたという、勇猛果敢かつ常識外れの精神力を持つその男・・・
「武道家、アラジン」
極度の緊張でカラカラに渇いてしまった喉の奥から絞り出すようにして、ドロシーはその名を口にした。
彼女の眼前には一人の青年が自然体で立っていた。そう大柄でも無い。どちらかと言えば小柄な方だ。
朴訥で真面目そうな、極めて普通の青年という印象だった。
母・カーレンとの厳しい修行を終え、
心身共に極限まで鍛え上げた万全の状態で満を持してやって来た、とある街の武術道場。
だが目の前に現れた道場主の風貌はあまりに凡庸で、
抱いていた印象とのあまりの落差に彼女は戸惑いを隠せずにいた。
(このヒトが本当にミュンハウゼンの一番弟子?)
そんな彼女の心の呟きに答えるかのように、青年は怪訝そうな表情で口を開いた。
「アラジンは私だが、何か?」
ドクン。早鐘のように脈打つ胸の鼓動を抑えるべく、大きく息を吸い込んでから彼女は答えた。
「ボクと、戦ってほしい」
途端、アラジンの眼光に鋭い光が宿った。
先ほどまでとは明らかに違う、武術の達人がそこにいた。
無言のまま見据えるアラジンの体の中で異常なまでに膨れ上がった闘気と覇気は、
やがて剛拳による一撃の如く彼女へと叩きつけられた。
常人ならば意識を保てるかどうかというほどの強烈な精神波動が彼女へと襲い掛かった。
だが、ドロシーは両脚をしっかりと大地に根付かせ、それを真正面から受け止めていた。
これほどの実力を持つ武術の達人と出会えた喜びと、
修行の成果を全力でぶつけられる相手を見つけた高揚感によって、彼女の体からすっかり緊張は消え、
逆に体の奥底から湧き上がる力が彼女をしっかりと支えていたのだ。
「・・・この覇気に圧されぬか」
アラジンは感心したような、それでいて半ば呆れたような表情を見せた後、
ゆっくりと右脚を踏み出しながら半身の体勢となり、そして身構えた。
「面白い。相手をしよう」
ドロシーは武者震い一つした後、大きく、力強く頷いたのだった。